学校からのお知らせ
News
【高校生向け】地方公務員と国家公務員の違いとは?職種・年収・向いている人を紹介
2024.06.15

地方公務員と国家公務員は、仕事内容や職種が大きく異なり、採用試験に関しても実施する組織が違います。
地方公務員と国家公務員という名前だけ聞いても、詳しい仕事内容や職種、年収などについては知らない方も多いのではないでしょうか。
同じ公務員でも仕事内容が大きく変わるため、自分の適性に合った職種を選ぶことが重要です。
この記事では、地方公務員と国家公務員の違いについて、職種や年収、向いている人などについて詳しく解説します。
地方公務員と国家公務員のどちらに就職するか悩んでいる学生さんは、ぜひ参考にしてください。
地方公務員と国家公務員の違いとは

公務員は、地方公務員と国家公務員の2つに分けられ、運営している機関や仕事の内容が異なります。
地方公務員は、都道府県や市区町村などの各自治体に所属しており、地域に密着した行政サービスを行う職業です。
採用試験も各自治体が実施し、試験内容についてもそれぞれで異なります。
国家公務員は、国が運営している行政組織や裁判を行う司法、議会の運営に係る立法などの機関に属しており、国全体における運営の仕事を行う職業です。
採用試験は人事院が実施しており、全国で共通の試験が行われます。
このように、地方公務員と国家公務員には、所属する組織や仕事の規模の違いがあります。
地方公務員と国家公務員の職種の違い

地方公務員と国家公務員では職種が異なります。
地方公務員と国家公務員の大まかな職種については以下のとおりです。
| 地方公務員 | 国家公務員 |
|---|---|
| 行政職 公安職 専門職 | 総合職 一般職 専門職 |
地方公務員は、地域に密着した仕事内容が多く、市町村職員は地域の住民との距離が近いため、自分が行っている仕事に対する喜びの声や住民の笑顔が実感できます。
また、国家公務員と比較して部署異動が多いため、さまざまな職務経験を積むことが可能です。
地方公務員の大まかな職種としては、行政職、公安職、専門職があります。
行政職は都道府県職員や市町村職員などがあり、地域住民の生活に関係する仕事を行います。
初級で担当する仕事は、主に一般事務や窓口業務が多いです。
また、公安職において地方公務員に該当するのは、警察官と消防官などがあげられます。
警察官は地域住民を犯罪から守り、地域の安全を維持する重要な仕事で、地方公務員として警察官になるには、都道府県の警察官採用試験への合格が必要不可欠です。
合格後は警察学校に入り、知識やスキルを学びます。
消防官は火災や災害、救急などの緊急性の高い危険から地域住民を守る仕事で、火災や災害の被害を抑えたり、事故や災害を未然に防止する活動を行う仕事です。
消防官は、各自治体が実施する公務員試験に合格する必要があり、合格後は消防学校で知識やスキルを学びます。
国家公務員は、社会に影響を与えるような規模が大きい仕事を行うため、よりよい社会の形成に貢献できる職業です。
専門職は地域ごとの採用が行われ、基本的に転勤することはありませんが、総合職は、全国規模における転勤の可能性があります。
地方公務員は、原則同じ地域で働く職種であるため、地域愛があるような方におすすめの職業です。
>関連記事『【高校生向け】公務員の種類はとても豊富!業種・職種を知って進路を選ぼう』
地方公務員と国家公務員の年収の違い

地方公務員と国家公務員の年収の違いにおいて、大きな差はありません。
国税庁の『令和3年分民間給与実態統計調査結果』によると、地方公務員の平均年収は約643万円で、人事院の『令和5年度国家公務員給与等実態調査』によると、国家公務員の平均年収は約681万円となっています。
職種によるばらつきはありますが、比較してみると大きな差はなく、どちらも高年収です。
また、公務員の平均年収は民間企業の平均年収よりも高いとされています。
国税庁の『令和3年分 民間給与実態統計調査』によると、民間企業の平均年収は約443万円となっています。
ただし、平均年収を比較した金額となっているため、公務員の全職業は民間よりも高いというわけではありません。
地方公務員は高卒でも目指せる職業であり、人気が高いため、おすすめの職業です。
>関連記事『公務員と民間の違いとは?仕事内容や給与など比較して進路を選ぼう!』
地方公務員と国家公務員の試験区分の違い
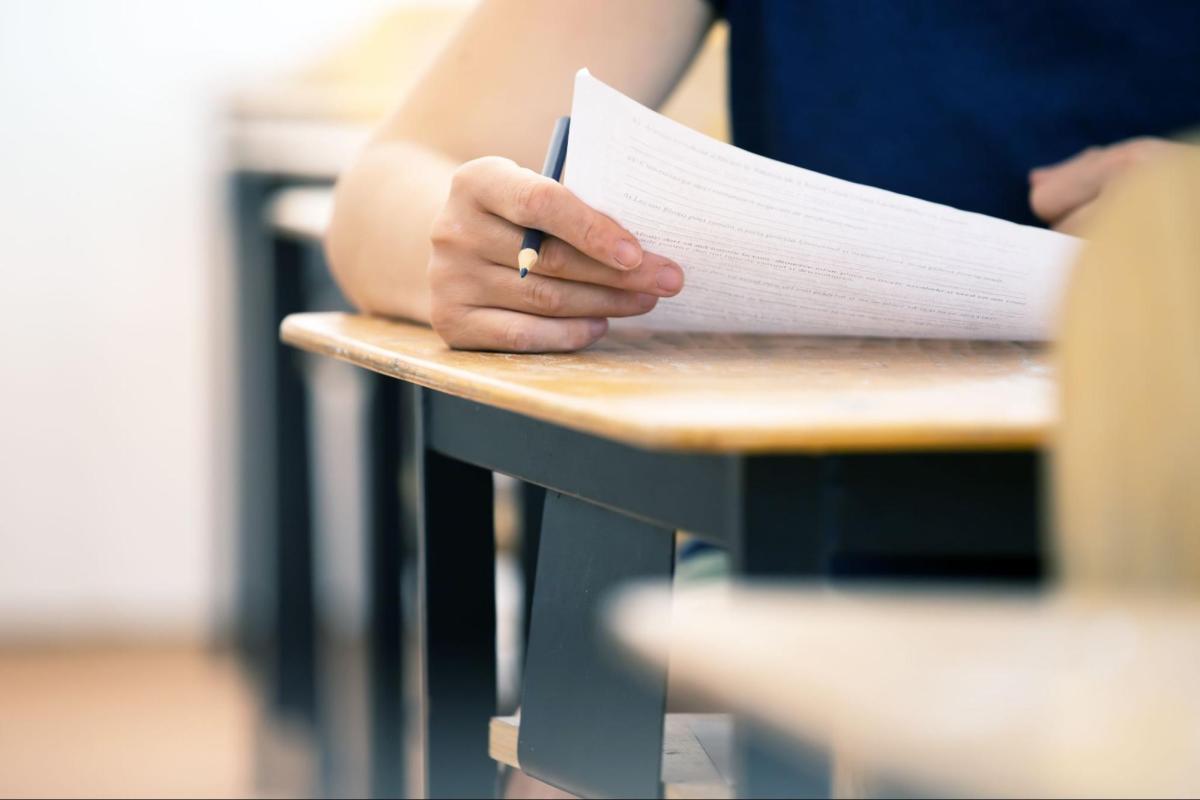
地方公務員は、都道府県や各自治体が実施する地方公務員採用試験を受験し、国家公務員は、人事院が実施する国家公務員採用試験を受験して、合格する必要があります。
地方公務員の試験は、各自治体によって試験内容や受験要件が定められていますが、大卒程度は上級、高卒程度は初級となっています。
ただし、上級の試験に関しては、大卒程度の学力が求められるような試験難易度を示しているだけであるため、高卒者でも受験可能です。
地方公務員の試験は、事務職や技術職などの区分も分けられているため、自分が受験する公務員試験の概要について確認しておきましょう。
>関連記事『【高校生向け】地方公務員初級の合格に向けたロードマップ!試験対策も徹底解説』
地方公務員と国家公務員の向いている人の違い

地方公務員と国家公務員は、仕事の内容や規模が大きく違うため、向いている人の違いがあります。
地方公務員と国家公務員に向いている人の特徴については以下のとおりです。
| 地方公務員 | 国家公務員 |
|---|---|
| 地域貢献を志す人 仲介役が得意な人 順応性が高い人 コミュニケーション能力が高い人 | 使命感や責任能力のある人 協調性のある人 グローバルな仕事に携わりたい人 |
地方公務員に向いている人の特徴
地方公務員は、各地域における総合的な運営を自主的に行う役割を持ち、地域のための行政サービスを行います。
したがって、地域住民と近い距離感で仕事を行うことが多いため、地域の役に立ちたい意欲や住民に寄り添った仕事をしたいという人は地方公務員に向いている人です。
また、都道府県職員は、市町村同士のやりとりを仲介する仕事をしたり、国と自治体の間に入ったりするような仲介役のような仕事を行う場合が多く見られます。
たとえば、災害発生した場合の緊急時には、被害状況の調査や避難所の運営は市町村が行い、都道府県が市町村からの情報提供を受けて、支援物資の依頼や自衛隊の派遣要請、人員的な応援の要請などを国に向けて行います。
複数の人の話を聞き、冷静に分析して冷静な判断を下し、仲介役として正確な情報を伝えられるような人は、国や市町村との仲介の仕事が向いているでしょう。
公務員は異動が多く、未経験の仕事を知識なしの状態から始める場合も多いです。そのため、順応性がありコミュニケーション能力が高い人は、新しい仕事に早く対応しやすいです。
もちろん、コミュニケーション力は、地域住民との対話をする際にも重要とされます。
国家公務員に向いている人の特徴
国家公務員は、地域に密着するというよりは、国全体の運営に関わるため、使命感や責任能力、協調性がある人が向いています。
国家公務員の仕事は、国の課題を解決してよりよい社会を作り国の未来を明るくすることです。
国の将来を決めるための政策の立案や実行、事務処理業務などを行うため、さまざまな専門的な知識が必要な仕事と言えます。
また、大規模な国の運営に関わる仕事であり、多くの人と一緒に仕事をしなければならないため、協調性が必要不可欠です。
したがって、国のために働く責任感と使命感を持ち、仕事を行うチームで協調性を発揮できる人は国家公務員として役割を果たせると言えます。
将来の働き方を考えて地方公務員と国家公務員を選択しよう

公務員試験を受ける際に国家公務員と地方公務員のどちらを選ぶかは重要な選択です。
地方公務員は地域に密着した仕事が多く、地元で働きたい人に適しています。たとえば、県庁や市役所で働くことができ、安定した生活がしやすいです。
一方で、国家公務員は国全体の政策に関わることが多く、スケールの大きな仕事をしたい人に向いています。中央省庁で働くことが多く、転勤することもあります。
どちらを選ぶかは、自分がどんな働き方をしたいかで変わり、自分の価値観や将来のプランを考えることが重要です。どちらが自分に合っているのか、しっかり考えて選択しましょう。
まとめ
地方公務員は都道府県や市町村の職員などの自治体に所属する公務員で、国家公務員は行政組織や司法、議会などの国が運営している組織に属している職員であり、運営している機関や職種、仕事内容が異なります。
地方公務員の職種は、行政職や公安職、専門職などがあり、地域に密着する形の仕事が多いです。一方で国家公務員の職種には、総合職、一般職、専門職があり、国の政策立案や実行に携わります。平均年収は、地方公務員と国家公務員で大きな差はありません。
地方公務員は地域貢献を志し、他人同士の仲介が得意で、コミュニケーションの高さで新たな場所でも順応しやすい人が向いており、国家公務員は国全体の課題解決に関心があり、使命感や責任感を持って働ける人が向いています。
地方公務員と国家公務員のどちらを選ぶかは、個人の価値観や将来設計によって変わってきます。地域に密着した仕事を希望するなら地方公務員、国全体の運営に関わる大規模な仕事を望むなら国家公務員が適しているでしょう。自分の適性や希望する働き方を考慮して、進路を選択することが重要です。
「立志舎グループ」の公務員カレッジは、公務員を専門としたカリキュラムを提供しており、公務員試験に合格するための効果的な学習ができる専門学校です。
公務員試験の対策に限らず、地域住民と接する際に役立つビジネススキルを学ぶことができ、クラスメイトと相談できて先生に授業内容を気軽に聞けるゼミ学習で楽しみながら理解を深められます。
警察官や消防官などの公安職を専門としたコースもあり、公務員試験の学習はもちろん、体力テストに向けたトレーニングもできます。
本校のオープンキャンパスでは、実際に通っている在学生の声を聞き、ゼミ学習の体感授業で雰囲気を確認できるので、ぜひこの機会に、立志舎公務員カレッジのオープンキャンパスに参加してみてはいかがでしょうか。

