学校からのお知らせ
News
【高校生必見】公務員試験の初級と上級の難易度の違いとは?合格するための勉強方法
2024.06.13

公務員試験は初級と上級があり、学習する難易度による違いがあります。
ただし、初級が簡単に合格できるというわけではないため、公務員試験においては適切な勉強や面接の対策をする必要があります。
この記事では、公務員試験の初級と上級の難易度の違いや、合格するための勉強方法について詳しく解説します。
公務員試験の難易度について知りたいみなさんは、ぜひ参考にしてください。
公務員試験の初級と上級の違いとは

公務員試験の初級と上級の違いは、主に試験の難易度に対応しています。
初級は高卒程度、上級は大卒程度といった形で、筆記試験に必要な学力の目安となっています。
大学を卒業していない場合でも、年齢による制限をクリアしていれば、上級試験を受けることが可能です。
ただし、受験の条件が大学卒業者や大学卒業見込みとなっている場合は、条件を満たす方しか受験できないため、注意が必要です。
公務員における試験区分ごとの難易度の違い
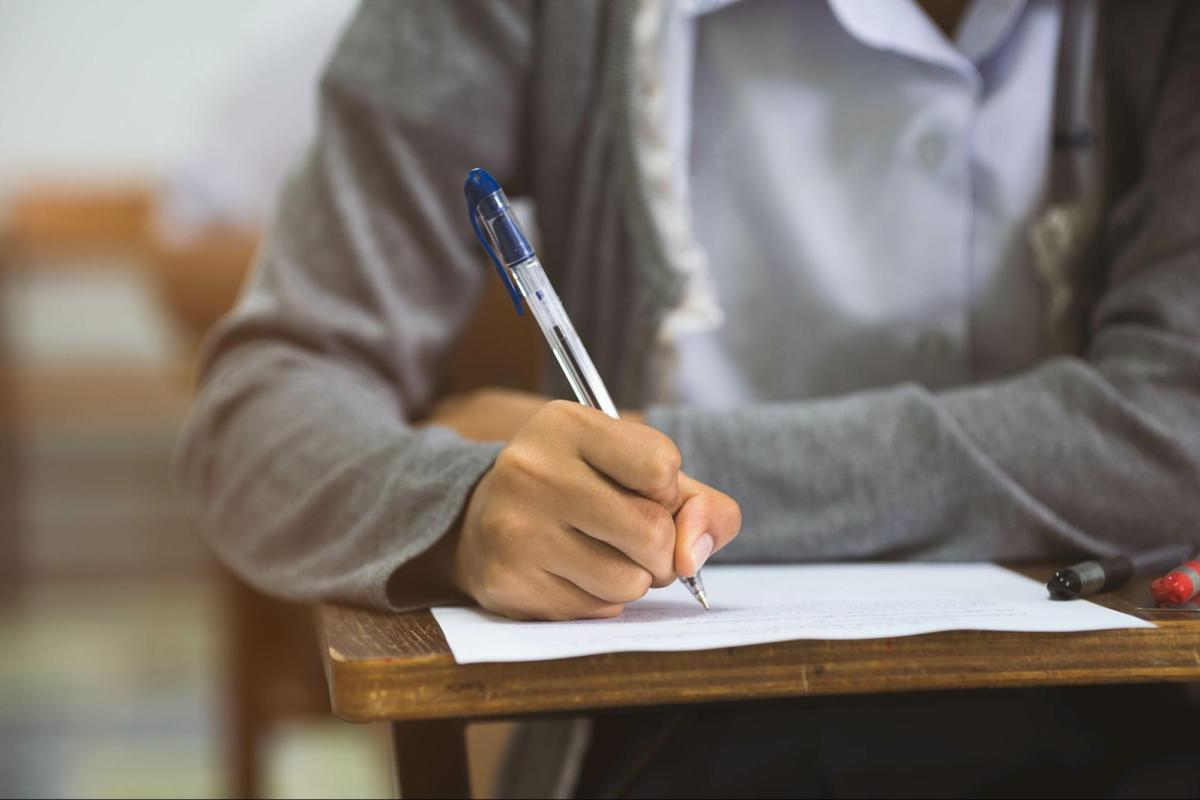
公務員試験の難易度は試験区分次第で大幅に変わります。
ここでは、試験区分ごとの難易度の違いについて説明していきます。
【高卒程度】地方公務員初級
地方公務員には、都道府県や市役所の職員、警察官、消防官などの職業があり、高卒程度の試験を行います。
市役所に関しては、中学レベルの問題が出題されるケースもあり、難易度は比較的低いです。警察官や消防官も筆記試験の難易度が比較的低く、併願して受験する人も多く見られます。
一方で地方公務員初級では、人物像的な部分をよく見られる場合が多いため、作文や面接の試験は、しっかり対策しておく必要があります。
【大卒程度】地方公務員上級
地方公務員上級は、地方自治体で働く行政職員や政令市職員などの職業があり、大卒程度の試験を行います。
地方公務員上級の試験は、高卒程度の試験よりは難易度が高いです。
たとえば都道府県職員は、比較的大きな地域単位で行政を担っており、都市開発や土地整備、道路や河川の整備などのさまざまな取り組みを行っています。
市町村や国、民間企業との連携を多く行いますが、市役所のような窓口での対応をすることはほとんどありません。
本庁以外にも、都道府県が運営している事務所や公共施設などに勤務する場合もあるため、転居が必要となるケースも見られます。
【大卒程度】その他の公務員
大卒程度の公務員には、国家総合職や国家公務員一般職などがあります。
国家総合職とは、官庁で働くキャリア官僚のことで、国の運営に関わる重要な役割を持つため、公務員試験のなかで最も難易度が高いとされています。
国家公務員の一般職も官庁で働く職員ですが、国家総合職よりも毎年の採用人数は多く、難易度は国家総合職ほど高いものではありません。
国家公務員一般職(大卒程度)は、大学を卒業した者及び、大学を卒業する見込みの者を対象としていますが、例外として、専門学校2年制を卒業した者及び、卒業する見込みの者も対象となります。
公務員初級の合格率

地方公務員初級は、受験者数が比較的多い傾向にありますが、都道府県や試験区分によって倍率・合格率が異なります。
地方公務員初級の倍率・合格率は、試験の実施主体から毎年度分が発表されています。
以下の表は、令和5年度の地方公務員初級や公安職試験の倍率・合格率についてまとめたものです。
| 機関 | 一次倍率(倍) | 二次倍率(倍) | 最終合格率(倍) |
|---|---|---|---|
| 特別区(事務Ⅲ類) | 1.98 | 1.5 | 4.3 |
| 千葉県警 警視庁(警察官B類) | 7.8(男性) 6.0(女性) | 7.1(男性) 5.3(女性) | 非公開 |
| 東京消防庁(消防官Ⅲ類) | 3.1 | 1.8 | 8.26 |
| 千葉県庁(一般行政職初級) | 1.5 | 1.7 | 3.04 |
| 神奈川県庁(行政職 3種) | 1.25 | 2.7 | 5.16 |
出典:特別区人事委員会、東京消防庁、千葉県庁、神奈川県庁、公務員試験総合ガイド
公務員初級の筆記試験と面接試験の難易度

公務員試験は、高卒程度と大卒程度で難易度が設定されています。
ここでは、公務員初級の筆記試験と面接試験の難易度について詳しく解説します。
筆記試験の難易度
公務員初級における高卒程度の筆記試験は、一般教養と作文で構成されており、公務員上級における大卒程度の筆記試験は、一般教養と専門試験、論文で構成されています。
高卒程度、大卒程度といった難易度の設定は、あくまで知識レベルの違いとして提示されている目安であるため、公務員試験を受ける前にどのくらいの難易度か確認しておきましょう。
面接試験の難易度
公務員初級の試験では、筆記試験の合格後に面接試験が行われますが、適切な面接対策を徹底することで、合格に大きく近づけます。
面接で求められる人物像は、ストレスに強くコミュニケーション能力が高い人だとされており、トラブルを起こさないような人が選ばれやすいです。
したがって、誠実さ、仕事への意欲、身だしなみが整っている人が合格しやすい傾向にあります。
面接の仕方は個人面接や集団面接など、受験する公務員によって異なりますが、面接方法ごとの面接対策をしておくことが重要です。
公務員初級に合格するための勉強の仕方

ここでは、地方公務員初級に合格するための勉強の仕方を紹介します。
出題数が多い科目の勉強
公務員初級の教養試験は出題範囲が広く多様な科目がありますが、出題数の多い科目から勉強を始めるのが望ましいです。
教養試験の出題科目については、以下のとおりです。
- 数的処理(数的推理・判断推理・資料解釈)
- 文章理解
- 人文科学
- 自然科学
- 社会科学
上記の出題科目のなかでも数的処理は出題数が多いため、早めに取り組む必要があります。
数的処理は、試験のうちの約3分の1の割合で出題されるケースもあり、得点を得るためには確実に押さえておきたいところです。
教養試験に対応できるようにするには、勉強を何回も反復しておくことが求められます。
出題数が多い科目を優先して勉強するために、出題傾向について知っておくことが重要です。
計画的に勉強する
公務員初級の勉強をする際には、具体的なスケジュールを立てる必要があります。
前述のとおり、公務員初級の教養試験は範囲が広いため、全ての科目を押さえるためには、計画的な勉強を行うことが重要です。
勉強の計画の立て方については以下のとおりです。
- 受験する職種の決定
- 試験概要の確認
- 必要な勉強時間の把握と配分
公務員初級の試験は、職種によって内容が異なるため、受験する職種に応じた勉強をする必要があります。
試験概要には、大まかな出題内容や解答方法について書かれているため、配点や時間配分についても確認しておくと安心です。
さらに、受験する公務員試験に合格するための、必要な勉強時間を把握しておけば、具体的な勉強時間の配分が可能となります。
勉強する時間配分を明確にしておけば、膨大な公務員試験の範囲を効率よく勉強できます。
試験までの勉強する内容を割り振っておき、細かくスケジュールを立てるようにしましょう。
過去問の活用
公務員初級の勉強をするなかで、過去問を活用すれば効率よく学習できます。
過去問を解くことで、出題側の意図や出題傾向を把握できるため、理解を深めやすいです。
公務員試験は毎年実施されていますが、同じ問題が出題されることが多々あり、過去問を分析しておけば、問題の解答が容易に行えます。
過去問に沿った内容を踏まえて、参考書で知識を深めるといった勉強方法がおすすめです。
時間制限を設けた練習
公務員初級の教養試験は、試験時間が定められています。
公務員試験には時間制限が設けられているため、全ての問題を解けないまま終わってしまうことも少なくはありません。
試験時間の配分を間違えてしまった場合、最後の問題まで解けなくなってしまうため、時間配分を意識して問題を解く練習をしておく必要があります。
また、練習していくうちに出題される問題のなかで、得意な問題や苦手な問題もわかってくるため、実際の試験でも解ける問題の判断がつきやすくなって効率よく解答できるようになります。
公務員試験によって問題の出題数や試験時間は異なるため、事前に必ず把握しておきましょう。
公務員専門学校に入学して公務員初級に合格しよう

公務員初級を目指す方は、公務員専門学校に入学して学習することで、より確実に合格へと近づけます。
公務員専門学校では、公務員試験に特化した教育課程を通して効果的に学習できます。
筆記試験の勉強に限らず、面接対策や基本的なビジネススキルについても学習できるため、万全な状態で公務員試験に挑むことが可能です。
また、公務員試験の最新情報に基づいた試験対策を把握でき、競争相手よりも優位に立ち回ることができます。
さらに、公務員を目指す仲間たちと教え合ったり、一緒に勉強したりして、高いモチベーションを維持した状態で日々の学習に取り組めます。
公務員初級の試験を受験する方は、公務員専門学校でしっかり学んで合格しましょう。
まとめ
公務員試験の初級と上級の違いは、試験の難易度の違いにあり、初級は高卒程度の学力、上級は大卒程度という形で、筆記試験に必要な学力の目安が設定されています。
また、公務員初級試験を上級と比較した場合に、試験自体の難易度は低い傾向があります。よって、頑張れば合格することは可能です。
自分で勉強する際のポイントとしては、出題数が多い科目の優先、スケジュールを立てる、過去問を活用する、時間制限を意識した練習などがありますが、公務員専門学校を利用すれば、適切な環境で勉強できるため、より確実に合格へと近づけます。
「立志舎グループ」の公務員カレッジは、公務員初級への合格を実現するためのカリキュラムを提供している専門学校です。
公務員初級コースでは、公務員試験に向けた学習はもちろん、ビジネスに求められる資格や知識を身に付けられ、就職する際の強みとして活かせられます。
教えることが得意な先生によるわかりやすい講義と、仲間同士で相談できる自由な学習ゼミで、理解して学習できる環境を備えています。
立志舎公務員カレッジのオープンキャンパスでは、進路の相談や公務員試験制度の解説、体感授業の体験ができますので、ぜひこの機会に参加してみてはいかがでしょうか。

